ホーム > 子育て・教育 > 子育て・児童家庭相談 > ヤングケアラー > 文京区の人材育成について > 令和6年度
更新日:2025年3月26日
ページID:10410
ここから本文です。
令和6年度
研修内容
第1回
|
研修名 |
第1回ヤングケアラー支援研修 「地域支援者とともにヤングケアラー発見について考える~発見してどうする?チームで支援するとは?~」 |
|---|---|
|
研修日時 |
令和6年9月27日(金曜日)13時30分から15時30分まで |
| 演者 |
|
|
受講人数 |
88名(相談機関職員、庁内職員、民生委員等) |
|
研修内容 |
文京区内の地域の居場所に関わる支援者にご登壇いただき、活動報告を行いました。 また、グループワークを通して、ヤングケアラーを発見する、チームで支援することについて考えました。 |
|
研修写真 |
|
第2回
|
研修名 |
第2回ヤングケアラー支援研修 「事例検討を通してヤングケアラー支援を考える~チームで支援する、かさなる、つながる~」 |
|---|---|
|
研修日時 |
令和6年11月18日(月曜日)14時から16時まで |
| 講師 | 杏林大学保健学研究科地域看護学研究室教授 大木 幸子 氏 |
|
受講人数 |
37名(相談機関職員、庁内職員等) |
|
研修内容 |
ヤングケアラーである子ども・若者の持つ困難さやチームでの支援について学びました。後半は、ヤングケアラーの模擬事例を用い、各支援機関においてどのような関わりができるのかグループワークを通して検討しました。 |
第3回
| 研修名 | 令和6年度文京区ヤングケアラー講演会 |
|---|---|
| 研修日時 | 令和7年2月5日(水曜日)14時から16時まで |
|
講師 |
一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 宮崎 成悟氏 |
| 受講人数 | 62名(文京区在住・在勤・在学者、庁内職員等) |
|
研修内容 |
ヤングケアラー当事者の経験から、ヤングケアラーの現状や当事者の思いを知り、地域での支援のあり方を学びました。質疑応答も多くあり、参加者の皆様の関心の高さがうかがえました。 講義では、家族の助け合いに頼ってきた日本の歴史から、ヤングケアラーのいる家庭がもつ課題の背景にあるものを考えました。また、家族や親せきなどの『強いつながり』と自分が安心する居場所などの『弱いつながり』、そして『自分との対話』を掛け合わせて関わっていくこと、そして、ヤングケアラーの状況は様々であるため、その多様さを理解し、年代に応じた対応が求められていることを学びました。ヤングケアラーにとって自身を気にかけてくれる大人の存在は大きなものであり、家族そしてヤングケアラー本人の声にまずは耳を 傾けることで支援の糸をたらし広げていけるとよいでしょう。 |
|
研修写真 |
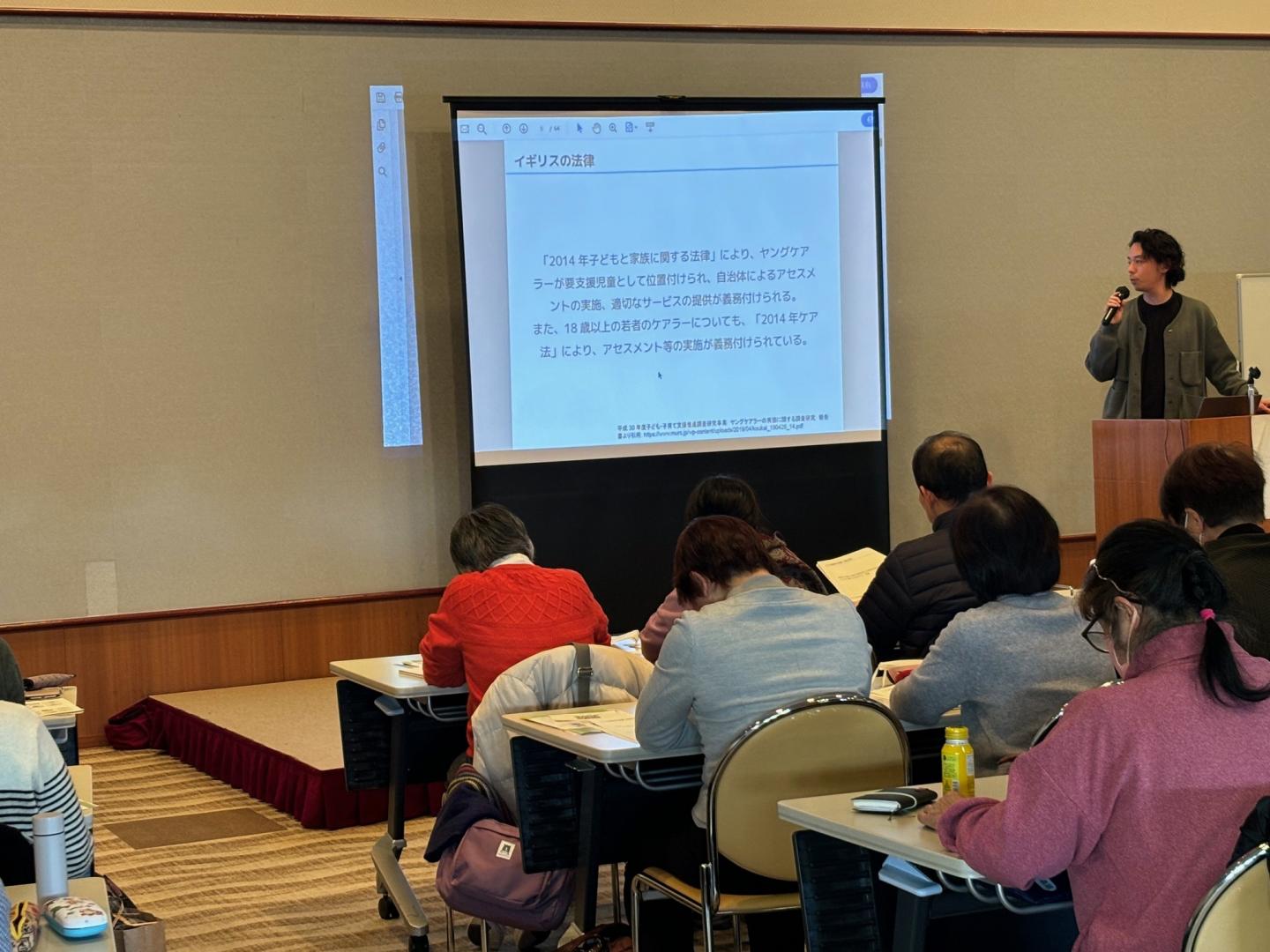 |
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター家庭支援係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1894
ファクス番号:03-5803-1345

