ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) > 学校給食に関すること > 「和食の日」の取り組み > 令和5年度「和食の日」の取り組み
更新日:2024年7月9日
ページID:9419
ここから本文です。
令和5年度「和食の日」の取り組み
毎月実施している「和食の日」給食
ユネスコ無形文化遺産に登録されたのは2013年12月。あれから10年が経ち、和食は世界的にもますます注目されるようになっています。和食は、栄養バランスが良い、素材のおいしさを味わうことができる、年中行事と密接な関わりがあり、季節の移ろいを感じることができるなど、優れた食文化です。文京区立小中学校では、毎月1回全校で一汁二~三菜を基本とする「和食の日」給食を実施しています。
新潟県魚沼市から新米が届きました。一粒一粒お米が立っています。

魚は下味を付けて焼きます。マヨネーズにすりおろしたにんじんを加えたソースをかけました。

青森県の郷土料理「せんべい汁」です。
使用するせんべいは汁物用に開発されたもので、煮込むとモチモチとした食感が特徴です。


副菜は、梅肉あえです。さっぱりとした味わいです。

当日の献立:魚沼産新米コシヒカリごはん、魚のもみじ焼き、梅肉あえ、せんべい汁、緑茶

これからも「いい日本食の日」給食を実施し、世界に誇れる和食を次世代の子どもたちに継承していきます。
学校の様子
魚沼産コシヒカリの日は、子どもたちがとても楽しみにしてくれているそうです。当日も真っ白なごはんをおいしそうに食べていました。魚沼産コシヒカリを給食でまた出してほしいとリクエストもありました。
11月24日は「いい日本食の日」給食
11月24日は「いい日本食の日」と制定されています。一人ひとりが和食文化の大切さを再認識するきっかけとなるよう願いが込められています。文京区立小中学校では、日本の食文化を深く学ぶ日として、この日は魚沼産新米と日本茶を提供しています。
ごはんが艶やかに炊き上がりました。お米が立っています。

魚(ホキ)は、下味を付けて片栗粉をまぶし、油で揚げて大根おろしのあんをかけました。揚げた魚にとろみがついたあんがよく絡みます。



副菜は、玉ねぎとじゃこのきんぴらです。玉ねぎの自然な甘みが活かされた、白いごはんによく合う一品です。



汁物は、じゃがいもと小松菜のみそ汁です。かつお節でとっただし汁に、じゃがいもを入れて、柔らかくなるまで煮たら、油揚げ・小松菜・長ねぎを入れます。味噌は最後に溶き入れます。



当日の献立:ごはん・魚のから揚げ大根あんかけ・玉ねぎとじゃこのきんぴら・じゃがいもと小松菜のみそ汁・緑茶

学校の様子
魚のから揚げには身が淡泊でやわらかいホキを使いました。外はカリッ、中はふわっとした食感のホキに、やさしい味付けのあんがたっぷりかかり、魚が苦手な子もおいしいと言って食べてくれました。「和食の日」給食は、和食の魅力を認識する良い機会となっています。
芋煮給食
令和5年の中秋の名月は9月29日でした。秋が深まるこの時期は、里芋の収穫時期に当り、芋名月とも呼ばれています。今回は、文京区と交流のある津和野町で収穫された里芋を使い、郷土料理「芋煮」を提供した学校の様子をお伝えします。芋煮は、鯛のアラと昆布で取った出汁に、鯛の身と下茹でした里芋を加え、薄味で調味します。仕上げに柚子を添えました。柚子がほのかに香る上品な一品です。
津和野町から取れたての里芋が届きました。粘りが強くて茹でると柔らかい里芋です。

里芋は下茹でをします。

新鮮な鯛が届きました。鯛の身は具に使います。アラは炙って出汁に使います。


炙った鯛のアラに昆布を加えて出汁を取ります。丁寧にアクを取ると澄んだ出汁が出来上がります。だし汁に里芋と焼いた鯛のほぐし身を入れて調味します。

仕上げに柚子皮を加えて出来上がりです。津和野町の芋煮は、すまし汁のようなシンプルな芋煮です。鯛のうま味と粘りが強い津和野町の里芋本来の味が際立ちます。

献立:ごはん、芋煮(島根県津和野町)、鶏の揚げ焼き、変わりきんぴら、ほうじ茶ゼリーミルクソース添え、緑茶

学校の様子
給食時間には、津和野町の紹介動画を視聴し、町の歴史や伝統を学びました。

子どもたちからは、「美味しい」「ゆずの香りがよかった」「鯛の出汁がおいしかった」「芋がモチモチして美味しかった」という声が聞かれました。当日は、津和野町に思いを馳せながら、よく味わって食べてくれたようです。残食もほとんど無く、大変好評でした。
日本三大芋煮とは
山形県のほぼ中央に位置する芋煮会発祥の地、中山町で生まれた鱈の干物を使った芋煮。
島根県の西端部に位置し「山陰の小京都」と呼ばれる津和野町に根付く、炙り小鯛を使った芋煮。
市の中央部を豊かな肱川が流れ、海山川の恵みが豊富な愛媛県大洲市に根付く、具沢山のいもたき。
この3つを日本三大芋煮と呼びます。


国内交流自治体の旅(岩手県盛岡市)給食
歌人、詩人として知られる石川啄木は岩手県盛岡市で生誕し、文京区小石川で没しました。この縁から友好都市を提携して5周年を迎えたことを記念して、令和6年2月20日、石川啄木ゆかりの給食を実施しました。「故郷の味は何にも比べられないぐらいおいしい」と石川啄木は言っています。そんな啄木思い出の味を給食で再現しました。食材には、盛岡市産の米と味噌を使いました。また、当日は盛岡市立小中学校でも同じ献立が提供されました。
献立:ごはん、すき焼き風煮、じゃがいもの味噌汁、牛乳

主食の「ごはん」は、岩手県盛岡市から取り寄せたオリジナルブランド米「銀のしずく」を炊きました。炊き上がりは白く艶やかでふっくらとしています。食べてみると、適度な粘りのモチモチ感があり、米の甘みが感じられます。冷めてもおいしいのが特徴です。
主菜は「すき焼き風煮」です。石川啄木は当時ごちそうだった馬肉をすきやき風にして食べたとされています。今回は、馬肉の代わりに豚肉を使い、思い出の味を再現しました。
汁物は、「じゃがいものみそ汁」です。文学仲間に宛てた手紙の中で、じゃがいもの味噌汁は何物にもかえがたい、と伝えています。味噌は、盛岡市産の“もりおか城下町みそ”を使いました。“もりおか城下町みそ”は、盛岡産の米“銀のしずく”と岩手県産の大豆“ナンブシロメ”を主原料とした味噌です。口の中いっぱいに素材のうま味が広がるおいしい味噌です。
学校の様子
当日は成澤区長と加藤教育長が学校を訪問し、児童と一緒に会食をしました。



給食時間には、石川啄木や盛岡産農産物についての説明動画を視聴し、文化や歴史の理解を深めました。
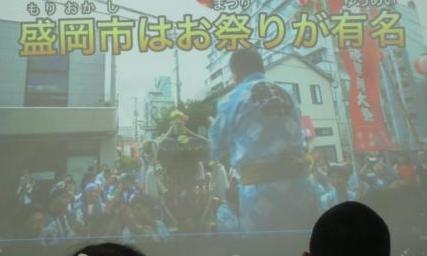
食を通して、先人への理解と親しみを持ち、盛岡市と友好を深め、両市がより発展していくことを願っています。
お問い合わせ先
教育推進部学務課給食指導担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1299
ファクス番号:03-5803-1367