更新日:2023年7月12日
ページID:2807
ここから本文です。
生食用牛レバーの販売・提供は禁止されています
平成24年7月1日から食品衛生法に基づいて、牛のレバー(肝臓)を生食用として販売・提供することは禁止されています。

これは、牛のレバーを安全に生で食べるための有効な予防対策は見いだせておらず、牛のレバーを生で食べると、腸管出血性大腸菌による重い食中毒の発生が避けられないからです。
腸管出血性大腸菌の危険性
- 牛のレバー内部には、「O157」などの腸管出血性大腸菌がいることがあり、食中毒が発生しています。
- 腸管出血性大腸菌は、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重い病気を引き起こし、死亡の原因にもなります。
区民のみなさまへ~これからも肉料理を安全に食べるために!!~
牛レバーは、すべて加熱用です。
- 一般的にレバーなどの内臓や食肉を生で食べると、食中毒を引き起こす可能性があります。
- 牛レバーの内部からも腸管出血性大腸菌が検出されたことが報告されています。
- 腸管出血性大腸菌による重い食中毒の危険性があるため、牛レバーは生では食べられません。
- 腸管出血性大腸菌は、少量の菌でも食中毒を引き起こします。
- 食中毒の発生に、「新鮮」かどうかは関係ありません。
必ず中心部まで加熱してから召し上がってください。
- 中心部まで十分火が通り、中心部の色が変わるまで、加熱して下さい。
- 中心部まで75℃1分間以上加熱すれば、腸管出血性大腸菌は死滅します。
生のレバーや肉と、その他の料理とは離して置き、調理器具も使い分けをしましょう。
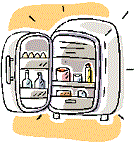
- 生のレバーなどの内臓や肉が触れたところには、菌がつく可能性があります。使った器具がその他の食品に触れないようにし、包丁やまな板は洗って熱湯をかけるなど消毒しましょう。
- 生のレバーや肉は、生で食べる野菜などど離して置きましょう。
- 加熱前のレバーや肉には、専用のトングや箸、皿を使いましょう。
牛レバー以外の肉の取扱いについて
- 生食用の基準を満たした牛肉・馬肉以外の豚肉や鶏肉等の内臓はすべて加熱用です。
- 食肉を冷蔵庫での保管の際は一番下の段にしまい、野菜などに肉の汁がつかないようにしましょう。
飲食店事業者のみなさまへ
新しい基準のポイント
(1)牛のレバーを原料として調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。
中心部の温度が63℃が30分間以上、または75℃で1分間以上の加熱をしなければなりません。
(2)牛のレバーは、「加熱用」として提供しなければなりません。
「生食用」「刺身」としての牛レバーの提供はできません。
(3)来店客が自ら調理するため、加熱していない牛のレバーを提供する際には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。

飲食店において、来店客が自ら調理して食べる場合には、飲食店はコンロや七輪などの加熱調理ができる設備を必ず提供してください。
飲食店事業者は、来店客が必ず牛のレバーを中心部まで十分に加熱して食べるよう以下3点を来店客に案内して下さい。
- 加熱用であること。
- 調理の際に中心部まで加熱する必要があること。
- 食中毒の危険性があるため生で食べられないこと。
もし、来店客が生や不十分な加熱のまま食べている場合には、十分加熱して食べるよう説明してください。
食肉販売店のみなさまへ
新しい基準のポイント
(1)牛のレバーは「加熱用」として販売しなければなりません。
「生食用」「刺身」として牛レバーの販売はできません。
(2)加熱されていない牛のレバーを販売する際には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
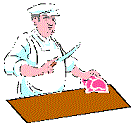
販売者は、消費者が牛のレバーを中心部まで十分に加熱して食べるよう以下3点を店頭に掲示するなどして、消費者に案内してください。
- 加熱用であること。
- 調理の際に中心部まで加熱する必要があること。
- 食中毒の危険性があるため生で食べられないこと。
関連リンク
お問い合わせ先
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386